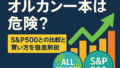本記事では、投資の基本から初心者におすすめのNISAやiDeCoまで実践的なステップを解説。
少額から安全にスタートする方法を知り、将来への不安を解消しましょう。
投資初心者は何から始めるべき?
まず最初にやるべきことは、いきなりお金を使って投資を始めることではありません。
投資をする際には、目的を明確にし、基礎的な知識を身につけておくことが大切です。
これにより、自分に合った投資方法を選べるようになり、リスクの取りすぎを防ぐことができます。
ここでは、投資初心者が最初に取り組むべき「目的の明確化」と「基本理解」について解説します。
投資の目的を明確にする
投資を始める前に、自分が「なぜ投資をしたいのか」をはっきりさせることが大切です。
目的が曖昧なままでは、商品選びに迷ったり、リスクの取り方を誤ったりする原因になります。
たとえば、「老後の資金を作りたい」「数年後の結婚資金を貯めたい」といった具体的な目標があると、必要な金額や期間、適した投資方法も見えてきます。
さらに目標が明確ならば、ブレない判断軸ができ、途中で不安になったときにも冷静に判断しやすくなります。
投資について理解を深める
投資には、株式や投資信託、債券などさまざまな種類があります。
どれも仕組みやリスクが異なるため、始める前に基本的な内容を知っておくことが重要です。
たとえば、投資信託はプロが運用を代行してくれるため、初心者でも始めやすいと言われています。反対に、株式投資は企業の業績や株価の変動を見極める知識が必要です。
「どんな仕組みで利益が出るのか」「どんなリスクがあるのか」を知ることが大切なのです。
投資による利益の得られ方
投資で得られる利益には「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2つがあります。
インカムゲインとは、資産を持っている間に得られる収入のことで、たとえば株の配当金や債券の利子などが該当します。
一方、キャピタルゲインは資産を売却して得られる差益のことです。たとえば、100万円で買った株が120万円に値上がりし、売却して得た20万円がキャピタルゲインになります。
投資ではこの2つの収益をうまく活用することが、資産形成のカギとなります。
投資の基本
投資で安定した成果を得るためには、基礎的な考え方を理解することが大切です。
ここでは、初心者がまず理解すべき「分散投資」「長期投資」「少額投資」の3つの基本戦略について紹介します。
分散投資
分散投資とは、資金を複数の投資先に分けることでリスクを減らす方法です。
1つの株や投資信託だけに資金を集中させると、その価格が下がったときに大きな損失につながります。しかし、異なる業種の株式や債券、投資信託などに分けておけば、一部が下落しても他の投資でカバーできる可能性があります。
さらに、投資のタイミングも分けておくと価格変動のリスクを平準化できます。これを「ドルコスト平均法」と呼び、毎月一定額を積み立てる方法としてよく使われています。
こうした工夫が、安定した資産形成につながります。
長期投資
長期投資は、数年から数十年かけて資産を運用するスタイルです。
短期的な価格の上下に左右されず、時間を味方につけることで「複利」の効果を得やすくなります。
複利とは利益が元本に加わり、次の利益を生むサイクルのことで、たとえば年利3%で運用すれば、10年、20年と経つごとに元本と利益がどんどん増えていきます。
短期間で大きな利益を狙うのではなく、コツコツと積み重ねていくのが長期投資の基本です。
少額投資
少額投資は、月1,000円〜数万円といった小さな金額から始められる投資方法です。
初心者でも手軽に始められるため、投資に慣れることが目的であれば、まずは余裕資金の範囲で少額から始めるのが安心です。
最近では、ネット証券を利用すれば100円単位で投資信託を購入できる商品もあります。
小さな金額でも積み立てを継続することで、将来的に大きな資産を作ることが可能なのです。
経験を積みながら、徐々に投資額を増やしていくのが理想的なステップになります。
主な投資の種類
投資初心者が検討しやすい代表的な商品として、「個人向け国債」「株式」「投資信託」の3つがあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った投資スタイルを選ぶことが大切です。
個人向け国債
個人向け国債は、国が発行する債券を個人が購入できるようにした金融商品です。
最大の特徴は「元本保証」がある点で、満期まで保有すれば元本が戻り、一定の利子が受け取れる点です。1万円から購入でき、金利が低くても元本割れの心配がないため、リスクを抑えたい初心者に適しています。
利回りは決して高くありませんが、資産を安全に保ちながら少しずつ増やす方法としては有効です。
また、途中で換金も可能で一定の条件下では手数料がかからないため、安定性を重視したい方には安心の選択肢です。
株式
株式は企業が資金調達のために発行するもので、購入者はその会社の一部を保有する株主となります。
株式投資では、株価の値上がりによる売却益(キャピタルゲイン)や、保有によって得られる配当金(インカムゲイン)が期待できますが、銘柄選びや売買のタイミングなどの判断が必要で、知識や情報収集力も問われます。
値動きが大きいためリスクはありますが、うまく運用できれば高いリターンを狙える手段です。
投資信託
投資信託は、複数の投資家から集めた資金を専門家が株式や債券などに分散投資する商品です。
1つの銘柄に集中せず、リスクを分散できるため、初心者にも始めやすいとされています。
さらに、少額から購入可能で、毎月一定額を積み立てる「積立型」も人気です。
運用はプロに任せられるので、投資の知識が少なくてもスタートしやすいのが魅力ですが、元本保証はなく、運用成績によって損失が出る可能性もあります。
そのため、投資信託は自分の目的に合ったファンドを選ぶことが重要になります。
初めて投資をする際のポイント
初めて投資を始めるときは、リスクを抑えながら安全にスタートすることが重要です。
ここでは、特に意識しておきたい「分散性」と「少額からのスタート」について解説します。
分散性
本記事の前半部分でも説明した通り、分散性(分散投資)を意識することは非常に重要です。
1つの金融商品や地域だけに資産を集中させると、予期せぬ値下がりが起きた際に損失が大きくなります。
たとえば、株式と債券、国内と海外といったように異なる種類や地域に分けて投資することで、リスクを抑えられます。
こうした分散投資は長期的に安定した運用を目指すうえで欠かせません。
少額から投資を初めてみる
初心者が投資を始める際は、いきなり大きな金額を投入するのではなく、少額から始めるのが賢明です。
仮に毎月1,000円〜5,000円程度の積立からスタートすれば、万が一値下がりしても損失は最小限に抑えられますし、少額であれば価格変動にも過度に不安にならず、冷静に投資の仕組みを学ぶことができます。
さらに近年では100円から購入できる投資信託などもあり、ハードルは低くなりつつあります。
まずは経験を積みながら、自分がどの程度リスクを許容できるのかを考えていきましょう。
投資初心者におすすめの金融商品
投資を始める際には、税制優遇があり、少額から始められる制度を活用するのが効果的です。
ここでは特に初心者に人気の高い「NISA」と「iDeCo」について紹介します。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからない仕組みです。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 運用スタイル | 積立投資 | 積立投資または一括投資 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税限度額 | 1800万円(うち成長投資枠は最大1200万円) | |
| 非課税保有期間 | 無制限 | |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等 |
| 解約・引き出し | 常時解約や引き出しが可能 | |
通常、株式や投資信託の売却益や配当金には約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座内で得た利益は非課税になります。
2024年から制度が刷新され、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれ、最大年間360万円まで投資できます。
特につみたて投資枠は、少額からコツコツ積み立てる形式で、初心者でも始めやすいのが特徴です。
iDeCo
iDeCoは、毎月一定額の掛金を自分で積み立てて運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る制度です。
掛金は月額5,000円から始められ、投資先は定期預金や投資信託など複数から選択できます。
最大のメリットは3つの税制優遇で、①掛金は全額所得控除、②運用益は非課税、③受取時にも所得控除が適用されます。
つまり、節税しながら効率よく資産を増やせる仕組みです。
途中で引き出しはできませんが、「長期・積立・分散」の効果が得られるため、コツコツと資産を育てたい初心者にも向いています。
少額投資(新NISA)を始めるための簡単5ステップ
1.NISA専用口座を開設するための金融機関を選ぶ
新NISA(つみたて投資枠)を始めるには、まず証券会社や銀行などの金融機関で専用の口座を作る必要があります。証券会社では「証券総合口座」、銀行では「投資信託口座」を開設し、その口座の中にNISA専用口座を設ける仕組みです。
なお、NISA口座は1人につき1口座しか持つことができません。複数の金融機関で同時にNISA口座を開設することはできないので、金融機関選びは慎重に行いましょう
2.口座開設の手続きを行い、本人確認書類やマイナンバー関連書類を提出する
金融機関が決まったら、口座開設の手続きを進めましょう。開設時に必要となる主な書類は、以下の通りです。
| 口座開設に必要な書類 |
| ・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーを確認できる書類 |
オンラインで申し込む場合は、必要事項を入力し、必要書類をアップロードします。
金融機関側で内容確認が済めば、仮の口座が開設され、すぐに取引ができるようになります。
対面での申し込みを希望する場合は、上記の書類を持参して店舗に行き、手続きを行ってください。
その際、本人確認書類に記載されている氏名や住所は、事前に登録した内容と完全に一致している必要があります。
3.口座開設のための審査を受ける
口座開設の申し込みが完了すると、税務署による審査が実施されます。審査のチェックポイントは以下の通りです。
- 提出された本人確認書類と申込者情報が正しく一致しているか
- すでに同一人物名義で口座が開設されていないか
審査が無事に終了すると、口座開設が承認された旨の通知が届き、それにより正式に口座が利用可能になります。
4.投資する商品(銘柄)を選定する
積立投資を始めるには、まず投資対象となる商品(銘柄)を選定する必要があります。
選べる商品は、金融庁の基準をクリアした「投資信託」および「ETF(上場投資信託)」に限られています。
また、各金融機関によって取り扱う商品ラインナップは異なるため、事前に確認しておきましょう。
5.積立の内容や金額などを設定し、購入の準備を整える
投資先が決まったら、積立の設定を行いましょう。
新NISAの「つみたて投資枠」では、一度設定すれば定期的に自動で買付が行われます。
金融機関によっては、100円や1,000円といった少額から積立を始められるため、初心者の方でも気軽にスタートできます。
なお、自動買付が継続されるため、引き落とし口座の残高は常に十分にしておくよう心がけましょう。
投資初心者によくある失敗
投資を始めたばかりの人が陥りやすい失敗には共通点があります。事前にこうしたケースを知っておくことで、リスクを抑えた堅実な投資が実現できます。
よく知らない商品に手を出してしまう
「儲かると聞いたから」「みんなが買っているから」といった理由で、仕組みやリスクをまり理解せずに金融商品を購入してしまうことも失敗の原因になります。
特に値動きが激しい仮想通貨やレバレッジ型ETFなどは、利益が出る可能性もある一方で、大きな損失を被るリスクがあります。
投資する商品は、仕組みやリスク、運用期間などを理解したうえで選ぶことが重要になるため、初心者は比較的安定していて情報も多い「投資信託」や「インデックスファンド」などから始めると安心です。
他人の意見を鵜呑みにしてしまう
SNSやYouTubeなどで紹介された情報をそのまま信じて投資するのも、初心者がよく陥るパターンです。
インフルエンサーが紹介している銘柄が必ずしも安全とは限りませんし、その人が実際に投資しているとも限りません。
さらに、報酬目的で紹介しているケースもあるため、情報の出所や信憑性を見極める力が必要です。自分で調べてみて、納得したうえで判断するようにしましょう。
生活資金まで投資に回してしまう
投資に慣れていない段階で、生活費や急な出費に備える資金まで投資に使ってしまうケースはよくあります。
今後数か月以内に必要になるお金を投資に回し、思わぬ下落で引き出せなくなれば、生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
投資は「余剰資金」で行うのが原則です。理想は6か月分程度の生活費を預貯金で確保したうえで、それ以外の資金を少額から投資に回しましょう。
価格が下がったときにすぐ売ってしまう
相場が下落したタイミングで「損をする前に」と焦って売却してしまうのも初心者に多いミスです。
たとえば、5%ほど値下がりした時点で売ってしまい、その後価格が回復するケースは珍しくありません。
投資では短期的な価格変動はつきものです。すぐに動かず、数年単位の視点で価格の回復を待つことも大切です。
あらかじめ「長期保有」を前提に計画を立てておくと、一時的な値下がりにも冷静に対応できるようになります。感情に左右されず、計画的な判断することが成功への近道です。
まとめ
投資を始める際は、目的を明確にし、分散・長期・少額という基本を押さえることが重要です。
利益の仕組みや主な商品、制度の特徴を理解したうえで、NISAやiDeCoといった制度を活用すれば、初心者でも無理なく資産形成を始められます。
いきなり大きな金額を投じたり、人の意見に流されたりすることなく、自分に合ったペースで、着実に投資を進めていくことが成功への第一歩です。
無理のない範囲で投資を始めてみてはいかがでしょうか?